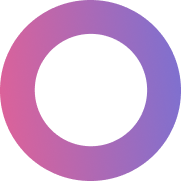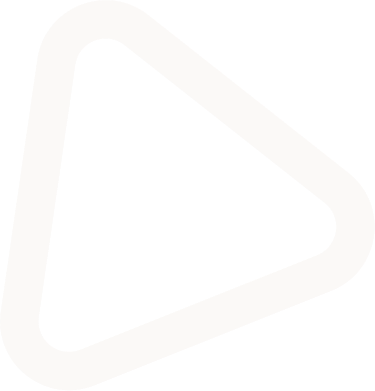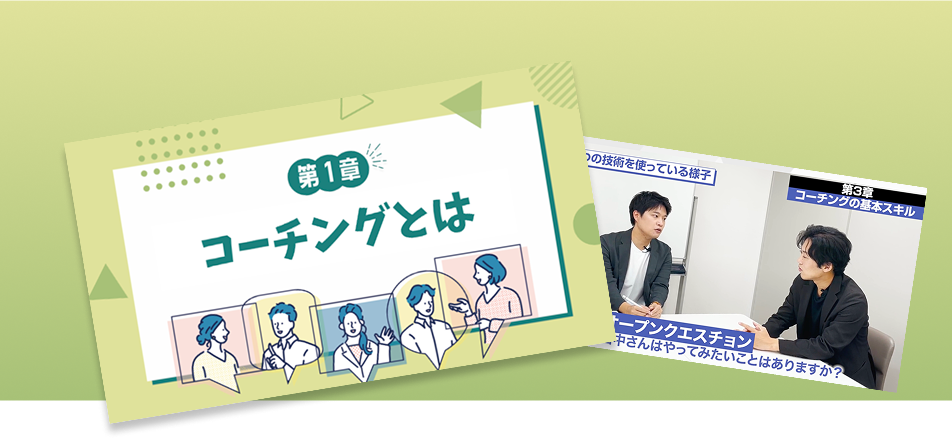仕事の成果は、最終的には「人」が生み出します。
だからこそ、組織にとって「人」をいかにマネジメントするかが、これほど重要なテーマとなっているのです。
特に近年は、働き方の多様化や価値観の変化により、従来の指示命令型のマネジメントでは対応が難しくなってきています。
そこで注目されているのが、コーチング型のピープルマネジメント。
メンバー一人ひとりの可能性を引き出し、主体的な行動を促すことで、組織全体の力を最大化する手法です。
この記事では、ピープルマネジメントの基礎から、コーチングを活用した実践的なアプローチまでを詳しく解説します。
1. ピープルマネジメントとは?

ピープルマネジメントとは、人材を活かし、育成し、組織の目標達成につなげる一連の取り組みのことです。
簡単に言えば、「人」を通じて組織の成果を上げる方法といえます。
たとえば、こんな場面を想像してみてください。

人気の居酒屋で、ベテラン店長の田中さんは、スタッフ一人一人の個性を見事に活かしています。
接客が得意な佐藤さんは お客様の多い時間帯に。料理の腕が良い鈴木さんはキッチンのピーク時に。
そして、新人の山田さんには、先輩たちと組み合わせて少しずつ経験を積ませていく。
チーム全体が生き生きと働いて、お店の雰囲気も良くなり、自然と売上も伸びていく…。
これが、まさにピープルマネジメントなんです。
つまり、ピープルマネジメントとは、「人」を通じて組織の成果を上げていく取り組みのこと。
一人一人の強みを活かし、成長を支援し、チーム全体の力を引き出していくことで、組織の目標達成につなげていくのです。
・適切な育成とサポート
・チーム全体の活性化
・組織目標の達成

得意を活かせば、誰もが主役になれる!
1.1 ピープルマネジメントの3つの柱
ピープルマネジメントにおいて、重要な3つの柱があります。
どれも欠かせない要素なのですが、どのように実践すればよいのでしょうか?
まずは全体像を見てみましょう。
- 人材活用:一人一人の才能を最大限に引き出す
- 人材育成:未来を見据えた成長支援
- 組織づくり:チームの力を結集する環境整備
たとえば、野球チームを思い浮かべてみてください。
監督は、選手一人一人の特徴を活かしてベストな打順を組み(人材活用)、
若手選手の育成に力を入れ(人材育成)、チーム全体の雰囲気を良くして強いチームを作っていく(組織づくり)。
このように、3つの要素がうまく噛み合って初めて、強いチームが生まれるのです。
1.1.1 人材活用 – 一人一人の個性を活かす

メンバーの適性や強みを見極め、最適な役割を任せることです。
簡単に言えば、その人の「得意」を活かすこと。
細かい作業が得意な人には品質管理を任せます。コミュニケーション力の高い人には調整役を。データ分析が得意な人にはプロジェクト評価を。
それぞれの才能が最も輝く場所で活躍してもらうのです。
適材適所の配置により、メンバーは自分の得意分野で活躍でき、自信とやりがいを持って仕事に取り組めます。
その結果、個人の成長と組織としての成果を同時に実現することができるのです。
1.1.2 人材育成 – 可能性を広げるサポート

人材育成とは、メンバーの成長をサポートし、新しいスキルや経験を積める機会を提供していくことです。
企業が実施する研修やトレーニングはもちろん大切ですが、実は日々の業務の中での成長支援こそが、最も重要な要素となります。
成長の機会は、身近なところにたくさんあります。
上司からの適切なフィードバックや助言、少し難しいと感じる挑戦的な課題、新しいプロジェクトへの参加など、様々な形があるでしょう。
最も大切なのは、上からの押しつけにならないこと。
メンバー自身が「成長している」「新しいことができるようになった」と実感できることが大切です。
この実感が、さらなる学びと挑戦への意欲を生み出し、持続的な成長へとつながっていくのです。
1.1.3 組織づくり – 力を結集できる環境をつくる

組織づくりとは、チーム全体がスムーズに機能するための環境を整えることです。
メンバー一人一人が持つ力を最大限に発揮し、チームとして大きな成果を生み出すための土台となります。
効果的な組織づくりには、いくつかの重要な要素があります。
まずは、全員が同じ方向を向いて進めるよう、組織の目標をしっかりと共有すること。
次に、メンバー間で必要な情報が適切に行き交う、円滑なコミュニケーションの仕組みを整えること。
そして、誰もが意見を言いやすく、前向きに仕事に取り組める、働きやすい雰囲気をつくることです。
このような環境が整うことで、メンバーは安心して自分の能力を発揮でき、
お互いの強みを活かし合いながら、チームとしての成果を最大化することができます。
・どれか一つが欠けても十分な効果は得られない

バランスを取りながら少しずつ改善を!
1.2 ピープルマネジメントが注目される背景
ここでは、、ピープルマネジメントが注目される背景について見ていきましょう。
1.2.1 働き方の多様化への対応

引用:Job総研による『2022年 副業・兼業に関する実態調査』を実施 コロナ禍を境に副業始める社会人4割増 今後始めたいは9割
ここ数年で、私たちの働き方は大きく変化しています。
コロナ禍を機に急速に広がったリモートワークは、もはや特別なものではなくなりました。
また、ライフスタイルや価値観の変化により、副業・兼業を行う人も増加。
さらに、フレックスタイム制の導入も一般的になり、従来の「9-5」の働き方が変わりつつあります。
対面でのコミュニケーションが減少する中、チームの一体感をどう保つのか。
これからのマネジメントには、柔軟性と創造性が求められます。
時間や場所にとらわれない新しい評価基準の確立、オンラインツールを活用したコミュニケーションの工夫、
そして多様な働き方を受け入れる組織文化の醸成が必要となっているのです。
1.2.2 価値観の変化への適応
働く人々の価値観は、この10年で大きく変化してきました。
かつての「仕事人間」的な生き方から、仕事と生活の調和を重視する考え方へとシフト。
また、一つの会社で定年まで働くという従来型のキャリアパスだけでなく、様々な選択肢を模索する人が増えています。
ワークライフバランスの重視は、もはや若手社員だけの傾向ではありません。
育児や介護との両立、自己啓発の時間確保など、従業員それぞれが大切にしたい生活領域があります。
企業には、これらへの理解と柔軟な対応が求められています。
1.2.3 ビジネス環境の変化への対応

ビジネス環境は、かつてないスピードで変化を続けています。
市場ニーズは日々変化し、テクノロジーは急速に進化。
このような状況下で組織が成功するためには、従来のマネジメントスタイルを見直す必要があります。
まず求められるのは、意思決定のスピードアップです。
現場のメンバーが状況を判断し、主体的に動ける環境づくりが重要になっています。
情報を持っている現場こそが、最適な判断を下せる場所なのです。
また、激しい競争を勝ち抜くためには、イノベーションが不可欠です。
従業員一人一人が持つ創造性を引き出し、新しいアイデアや解決策を生み出せる環境を整えることが、これまで以上に重要になっています。
1.3 従来型マネジメントとの違い
マネジメントのスタイルは、時代とともに大きく変化してきています。
従来のマネジメントといえば、上司からの指示命令が中心でした。
「何を」「どのように」すべきかを細かく指示し、部下はそれに従うというスタイル。
この方法は、やるべきことが明確な業務遂行には効果的でした。
しかし、変化の激しい現代では、必ずしも最適とは言えなくなっています。
そこで注目されているのが、個人の主体性を重視するピープルマネジメントです。
メンバー一人一人の考えや判断を尊重し、自発的な行動を促していく。
その人が持つ可能性を最大限に引き出すことで、組織全体の力を高めていく手法です。
1.3.1 マネジメントスタイルの比較
| 項目 | 従来型 | ピープルマネジメント |
| 基本姿勢 | 管理・監督 | 支援・育成 |
| コミュニケーション | 一方向 | 双方向 |
| 目標設定 | トップダウン | 対話による共有 |
| 評価重点 | 結果 | プロセスと成長 |
| 動機付け | 外発的(報酬・罰則) | 内発的(自己実現・成長) |
このような違いが生まれた背景には、ビジネス環境の変化があります。
かつての安定的な経営環境では、上司の経験則に基づく指示で十分に機能していました。
しかし、現代のように変化の激しい環境では、現場レベルでの柔軟な判断や創意工夫が不可欠です。
そのため、メンバー一人ひとりの主体性を引き出し、チーム全体の力を最大化するピープルマネジメントが重要になってきているのです。
・個人の可能性を引き出す
・成長と成果の両立を目指す
1.3.2 具体的な違いの例
従来型とピープルマネジメントでは、日常的なコミュニケーションの在り方が大きく異なります。
ここから、詳細を見ていきましょう。
指示の出し方
上司が考えた解決策をそのまま伝え、メンバーはその通りに実行するだけ。
確かに効率的ですが、メンバーは単なる作業者となり、創意工夫の機会が失われてしまいます。
上司とメンバーが一緒に複数の解決策を検討し、最適な方法を見つけていきます。
この過程で、メンバーの主体性が育まれ、創造的な解決策が生まれる可能性も高まります。
問題発生時の対応
この方法では、メンバーは自己防衛的になり、言い訳に終始しがちです。
結果として、表面的な対応で終わってしまい、本質的な課題解決には至りません。
メンバーとの対話を通じて真の課題を特定し、一緒に解決策を考えていきます。
この過程で、メンバーは問題解決能力を身につけ、次に活かせる貴重な学びを得ることができます。
この違いは、単なるアプローチの違いではありません。
メンバーの成長機会をどう捉えるか、という根本的な考え方の違いを表しているのです。
問題を責めるのではなく、成長のきっかけとして活かす。それがピープルマネジメントの本質です。
目標達成に向けて
プレッシャーをかけることで短期的な成果を引き出そうとしますが、その代償としてメンバーのストレスが蓄積されやすく、長期的にはモチベーションの低下を招きかねません。
建設的な対話を通じて課題を共有し、必要な支援を適切なタイミングで提供します。
この方法では、メンバーは前向きに目標に取り組むことができ、持続的な成果につながります。
・メンバーの主体性を重視する
・対話を通じた相互理解を大切にする

小さな会話の積み重ねが、大きな違いを生みます!
2. コーチング型ピープルマネジメントの特徴
 部下を育てたい。
部下を育てたい。
でも、どうすればいいのかわからない。
そんな悩みを抱えるマネジャーは多いのではないでしょうか。
ここでは、効果的な育成手法として注目を集めているコーチング型ピープルマネジメントについて、詳しく見ていきましょう。
2.1 なぜコーチングが効果的なのか
人は誰でも、可能性を秘めています。
コーチングは「答えはその人の中にある」という基本理念に基づいています。
この考え方は、現代のピープルマネジメントが直面する様々な課題に対して、効果的な解決策となります。
従来型の指示命令では引き出せなかった、メンバー一人ひとりの潜在的な可能性を開花させることができるのです。
2.1.1 コーチングの基本的な考え方
コーチングでは、マネジャーは答えを与える存在ではなく、メンバー自身が答えを見つけ出すプロセスをサポートする存在です。
たとえば、新しいプロジェクトの進め方を決める際、従来型のマネジャーが経験則に基づいて「こうすべき」と指示するのに対し、
コーチング型のマネジャーは「どんなアプローチが考えられる?」と問いかけ、メンバーのアイデアを引き出します。
時には、遠回りも必要です。
このような関わり方の違いは、短期的には時間がかかるように見えても、長期的には大きな成果の差となって現れてきます。
メンバーの思考力が鍛えられ、創造性が刺激され、そして何より、主体的に課題に取り組む力が育っていくからです。
| アプローチの違い | 従来型 | コーチング型 |
| 基本姿勢 | 答えを教える | 答えを引き出す |
| 対話の特徴 | 一方向の指示 | 双方向の対話 |
| 期待する効果 | 即時的な課題解決 | 長期的な成長 |
2.1.2 主体性を引き出す効果

自分で考え、決断し、行動することには、明確なメリットがあります。
自ら考え抜いた解決策には特別な思い入れが生まれます。
「これは自分で選んだ方法だ」という意識が、困難に直面しても諦めない粘り強さを生み出します。
誰かに言われたことをやるのとは、根本的に異なる力が湧いてくるのです。
また、既存の枠にとらわれない発想が生まれやすく、チーム全体のイノベーション力も高まっていきます。
小さな成功が、大きな自信になります。
この経験の積み重ねが、組織全体の力を高めていくのです。
・創造性と革新性が自然と育まれる
・成功体験が次への原動力となる
2.2 期待できる具体的な効果
組織にコーチング型のマネジメントを導入すると、どのような変化が生まれるのでしょうか。
では、具体的にどのような効果が期待できるのか。以下、詳しく見ていきましょう。
2.2.1 個人の成長とモチベーション向上
コーチング型マネジメントがもたらす最も大きな効果の一つが、メンバー一人ひとりの成長とモチベーションの向上です。
従来型の「言われたことをやる」スタイルから、「自ら考え、決断する」スタイルへの転換は、仕事への向き合い方を大きく変えていきます。
その具体的な効果は、以下のような形で現れます。
| 項目 | 効果 | 具体例 |
| 主体性 | 自発的な行動が増える | 課題の事前把握と対策提案 |
| 創造性 | 新しいアイデアが生まれる | 業務改善提案の増加 |
| 責任感 | 最後までやり抜く力が育つ | 困難な課題への粘り強い取り組み |
2.2.2 チームパフォーマンスの向上
個人の成長は、やがてチーム全体の力となって実を結びます。
それは、単なる個々の力の総和以上の価値を生み出していきます。
メンバー同士が互いの考えを尊重し、建設的な対話を重ねることで、チームの問題解決力は着実に高まっていきます。
「自分だけ」ではなく「チームで」という意識が自然と芽生え、新しいアイデアや解決策が次々と生まれてくるのです。
さらに、以下のような相乗効果も期待できます。
誰かが困っているときは、声がけがなくても自然とサポートの手が伸びる。このような協力関係が日常的に生まれます。
・情報共有の活性化
「この情報は役立つかも」と、必要な情報が自発的に共有されるようになり、チーム全体の情報力が高まります。
・相互学習の促進
お互いの得意分野を教え合い、学び合う文化が育ちます。これにより、チーム全体のスキルレベルが向上します。
・チーム全体の生産性向上
これらの要素が組み合わさることで、チーム全体の生産性が大きく向上していきます。
2.2.3 組織文化の変革
コーチング型マネジメントの最も大きな価値は、組織文化そのものを変革できることにあります。
それは、単なる制度や仕組みの変更ではなく、組織の在り方そのものの転換を意味します。
一人ひとりが主体的に考え、積極的に挑戦し、日々成長を続ける。
このような前向きな姿勢が、組織全体に確実に根付いていきます。
「失敗を恐れない」「新しいことにチャレンジする」「互いに学び合う」。
そんな風土が自然と形成されていくのです。
そして、この文化がさらなる個人の成長を促すという、好循環が生まれていきます。
・対話を通じてチーム力が高まる
・挑戦を称賛する文化が根付く

成果は必ず後からついてきます!
2.3 マネジャーに求められるスキル
コーチング型マネジメントを効果的に実践するには、マネジャー自身にもスキルが求められます。
これは特別な才能というわけではなく、意識的な実践で徐々に身についていくものです。
完璧なスキルは必要ありません。
大切なのは、メンバーの成長をサポートしたいという意志と、自身も学び続ける姿勢です。
マネジャー自身が成長のプロセスを楽しみながら、必要なスキルを磨いていけばよいのです。
2.3.1 基本的なコミュニケーションスキル
効果的なコーチングの土台となるのが、質の高いコミュニケーションです。
言葉を交わすだけでなく、メンバーの成長を支える深い対話が求められます。
特に重要なのは、以下の3つです。
| 積極的な傾聴 | 単に話を聞くのではなく、メンバーの言葉の背景にある思いや考えにも耳を傾けます。 うなずきや相槌、表情などの非言語コミュニケーションも大切な要素です。 |
| 効果的な質問 | 答えを示すのではなく、メンバー自身の「気づき」を促す問いかけを心がけます。 「どう思う?」「他にどんな方法がある?」といった開かれた質問が、考えを深めるきっかけとなります。 |
| 適切なフィードバック | 具体的で建設的なフィードバックを提供します。 良い点は積極的に認め、改善点は成長の機会として伝えます。 タイミングと伝え方にも配慮が必要です。 |
2.3.2 実践的なマネジメントスキル
| スキル | 内容 |
| 目標設定 | チャレンジングだが達成可能な目標設定 |
| 進捗管理 | 定期的な確認と必要な支援の提供 |
| 評価育成 | 成長を促す建設的なフィードバック |
これらのスキルは、日々の実践を通じて徐々に磨かれていきます。
大切なのは、メンバーの成長を心から支援したいという意志と、自身も学び続ける謙虚な姿勢です。
マネジャー自身が成長を楽しむ姿勢を見せることで、メンバーも前向きに取り組めるようになります。
・実践を通じて力をつける
・完璧を目指さず、一歩ずつ進める

成長は互いに学び合う過程です!
3. 実践!コーチング型ピープルマネジメント
 理論は理解できても、実践となるとどうすればいいのか。
理論は理解できても、実践となるとどうすればいいのか。
そんな疑問を持つ方も多いはずです。ここからは、具体的な実践方法を見ていきましょう。
3.1 1on1ミーティングの活用術
1on1ミーティングは、コーチング型マネジメントの基本となる重要な場です。
単なる進捗確認の場ではなく、メンバーの成長を支援する貴重な機会として活用しましょう。
3.1.1 効果的な1on1の進め方
まずは実演動画を見てみましょう。
基本的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 準備 | 議題の設定 | メンバーに事前に考えてもらう |
| 対話 | 現状の確認と課題の明確化 | 傾聴と質問を意識する |
| まとめ | 次のアクションの設定 | 具体的な行動に落とし込む |
・メンバーが話しやすい雰囲気をつくる
・具体的なアクションにつなげる

対話の質が成果を左右します!
3.2 効果的な質問技法
適切な質問は、メンバーの気づきと成長を促します。
答えを教えるのではなく、メンバー自身が考え、発見するきっかけを作ることができます。
3.2.1 質問の基本パターン
問いかけ方一つで、メンバーの思考の深さは大きく変わります。
以下のような質問を状況に応じて使い分けましょう。
| 質問のタイプ | 具体例 | 目的 |
| 状況把握 | 「今の状況をどう捉えていますか?」 | 現状認識の確認 |
| 掘り下げ | 「それについてもう少し詳しく教えてください」 | 理解の深化 |
| 未来志向 | 「理想的な結果とはどんなものですか?」 | 目標の明確化 |
| 行動促進 | 「次のステップとして何ができそうですか?」 | 具体的な行動の引き出し |
このような問いかけにより、メンバーは自ら考え、答えを見つけ出す力を養っていきます。
答えを急がず、考える時間を十分に取ることも大切です。
– 相手のペースを尊重する
– 一つの質問に絞る
– 答えを誘導しない
・質問の意図を明確にする
・相手の思考を促す問いを心がける

良い質問は、新しい視点を開きます!
4. コーチング型マネジメントの実践ポイント

理論と基本を理解していても、実践では様々な課題に直面します。
特に重要なのが、メンバー一人一人の個性に合わせたアプローチです。
全員に同じ方法を適用しても、効果的な結果は得られません。
4.1.1 タイプ別の効果的な関わり方
| タイプ | 特徴 | 効果的なアプローチ |
| 積極型 | 自ら意見を述べる | 考えを整理する支援 |
| 慎重型 | じっくり検討する | 十分な検討時間の確保 |
| 実践型 | 行動が早い | 振り返りの機会の提供 |
| 分析型 | データを重視 | 根拠に基づく対話 |
メンバーの個性は、決して「扱いにくさ」ではありません。
むしろ、チームの大きな強みとなります。
積極型のメンバーが新しいアイデアを出し、慎重型がリスクを指摘し、実践型が素早く行動に移し、分析型が効果を検証する。
このように、異なる個性が組み合わさることで、チーム全体のパフォーマンスが高まっていくのです。
・柔軟なアプローチを心がける
・その人らしさを活かす
5. 実践における課題と解決策
 理想のマネジメントは理解できても、現実の職場では様々な課題に直面します。
理想のマネジメントは理解できても、現実の職場では様々な課題に直面します。
しかし、これらの課題は決して乗り越えられないものではありません。
適切な対処法を知り、一つずつ解決していくことで、より良いマネジメントを実現できます。
5.1 よくある課題と対処法
実践の現場では、多くのマネジャーが共通の課題に直面しています。
例えば、「時間がない」「メンバーが受け身」「成果が見えにくい」といった悩みは、よく聞かれるものです。
これらの課題に対して、具体的にどのように対処していけばよいのか。
実践的な解決策を、一つずつ見ていきましょう。
5.1.1 主な課題とその対処法
| 課題 | よくある状況 | 効果的な対処法 |
| 時間不足 | 「1on1の時間が取れない」 | 短時間でも定期的な実施を優先 |
| スキル不足 | 「うまく質問できない」 | 基本的な質問から始める |
| 反応の乏しさ | 「メンバーが話してくれない」 | 雑談から関係性を築く |
| 成果が見えない | 「効果が実感できない」 | 小さな変化に注目する |
これらの課題に対しては、完璧を目指すのではなく、できることから着実に進めていく姿勢が重要です。
一足飛びの改善は難しくても、小さな成功を積み重ねることで、確実な前進が可能となります。
例えば、スキル不足を感じる場合は、まずは基本的な質問から始めます。
「どう思う?」「何か困っていることは?」といったシンプルな問いかけから始めて、徐々にレパートリーを増やしていけばよいのです。
また、失敗を恐れる必要はありません。
むしろ、それを学びの機会として捉え、自分なりのやり方を見つけていくチャンスです。
大切なのは、継続できる方法を確立すること。
そのためには、無理のないペースで着実に実践を重ねていくことをお勧めします。
・できることから着実に進める

失敗も大切な経験です!
まとめ
コーチング型ピープルマネジメントは、これからの時代に求められるマネジメントスタイルです。
完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ始めることが大切です。
日々の小さな実践の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。
そして、その変化は組織全体の成長へとつながっていくのです。
まずは、あなたの周りのメンバーとの対話から始めてみませんか?
・継続的な実践を心がける
・組織全体の成長を目指す

一歩からすべては始まります!
コーチングを身に着けるならFIRST COACH

オンライン特化型コーチングスクール FIRST COACHでは、業界最安値の価格で実践的なコーチングスキルを身に着けることが可能です。
基本からプロレベルまで「現場で使えるコーチング」を専属コーチとの二人三脚で身につけましょう。
新たな可能性を自分自身で広げる一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?
今ならフリーコースとして無料でコーチングの基礎を学び放題。
これからコーチングのスキルを身につけたい方は、ぜひFIRST COACHを受講してみてください!