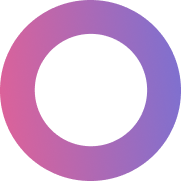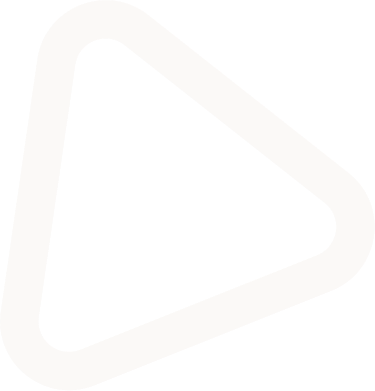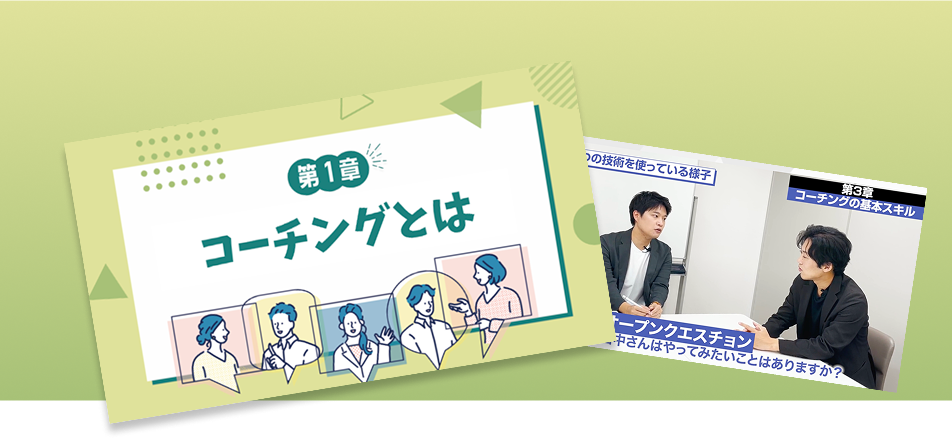介護の現場で「もっと良いケアがしたい」「職場の雰囲気を改善したい」「スタッフの成長を支援したい」。
そんな思いを抱える方は少なくありません。
日々の業務に追われ、コミュニケーションに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、これらの課題を解決する効果的な手法があります。それが「コーチング」です。
単なるコミュニケーション技術ではなく、現場を変える強力なツールとして注目されています。
今回は、介護現場ですぐに実践できるコーチングの具体的な方法についてご紹介します。
1. コーチングの基礎知識
1.1 介護現場でのコーチングとは

コーチングとは、質問を通じて相手の考えや可能性を引き出し、成長を支援する手法です。
単なる指導や助言とは異なり、質問を通じて相手自身の「気づき」を促すことに重点を置きます。
従来の介護現場での指導は、「このように介助してください」「次はこうしましょう」といった、指示や教示が中心でした。
しかし、介護の現場では状況が刻々と変化します。利用者さん一人ひとりの体調や気分も日々異なり、画一的な対応では十分なケアを提供できません。
そこで重要になるのが、スタッフ自身が考え、判断し、行動する力です。
コーチングは、まさにこの力を育てるための効果的な手法なのです。
スタッフ「最近、箸を持つ時間が長くなっているように感じます」
リーダー「なるほど、そこに気づいたのですね。他に気になる点はありますか?」
スタッフ「はい、食事中の会話も少なくなっているように思います」
リーダー「細かな変化によく気づいていますね。では、どのようなアプローチができそうですか?」
・具体的な観察を引き出す

スタッフの自律性を育て、柔軟な対応を支援するという点が重要ですね。
1.2 なぜ介護現場でコーチングが重要か
介護の現場では、日々新しい課題に直面します。利用者さんの状態は常に変化し、その変化に応じて適切なケアを提供する必要があります。
そのため、マニュアルや決められた手順だけでは対応できない状況が頻繁に発生します。
コーチングを活用することで、以下のような効果が期待できます。
・予防的なケアが可能になる
・状況に応じた柔軟な対応が可能に
・多角的な視点でケアを考える
さらに、コーチングは職場の雰囲気改善にも効果的です。
「自分の意見が尊重される」「気づきを共有できる」という環境は、スタッフのモチベーション向上につながり、結果として離職率の低下にも寄与します。
1.3 介護現場での活用シーン
「なぜ、この利用者さんは食事量が減ったのだろう?」「どうしたら、もっと楽しく入浴していただけるだろう?」
介護の現場では、日々たくさんの”気づき”や”疑問”が生まれます。
コーチングは、こうした場面で大きな力を発揮します。例えば、食事介助後のこんな会話が、新たな気づきを生みます。
スタッフ「今日は、野菜から手を付けられていました」
リーダー「それは興味深いですね。普段と違う点に気づきましたか?」
スタッフ「そういえば、いつもより会話も多かったように思います」
認知症ケアでは、「なぜこの行動をとられるのか」「どんな気持ちが隠れているのか」といった問いかけが特に重要です。
この視点での対話を重ねることで、利用者さんへの理解が深まり、より適切なケアが見えてきます。
このように、コーチングは介護現場の様々な場面で、より良いケアを実現するための強力な武器となるのです。

利用者理解が深まりますね。
2. 実践的なコーチング技法
2.1 “聴く”技術

聴くことは、単に耳で音を感知するだけではありません。
相手の言葉に込められた思いや意図を理解しようと積極的に取り組む行為なのです。
特に介護の現場では、この「聴く」技術が非常に重要となります。
利用者やスタッフの話を聞く際は、以下のようなポイントに気をつける必要があります。

相手の内面に寄り添う姿勢が何より大切
2.1.1 相手の話を遮らない
例えば、利用者が自分の近況について話し始めたとします。
その際、あなたが「そうですね」や「はい」と割り込むのではなく、利用者が最後まで話し終えるまで待つことが大切です。
相手の話を遮らずに最後まで静かに聞く姿勢を持つことで、相手の思いをより深く理解することができるでしょう。
2.1.2 適切なタイミングで相づちを打つ
相手の話を理解していることを示すために、うなずきや「はい」といった相づちを打つのはよい方法です。
ただし、あまりにも頻繁に相づちを打ったり、不適切なタイミングで打つと、かえって相手を遮っているように感じられてしまう可能性があります。
適切なタイミングと頻度で相づちを打つよう心がけましょう。
2.1.3 表情や仕草にも注目する
相手の言葉だけでなく、表情や仕草にも注目することで、より正確な理解につなげることができます。
例えば、利用者が話している最中に表情が曇ったり、手を握り締めたりするような仕草が見られた場合、その背景にある気持ちを推察することができます。
2.1.4 内容を整理して確認する
相手の話を聞き終えたら、その内容を整理して確認することで、相手の意図をより正確に理解できます。
必要に応じて、「先ほど○○と仰っていましたが、その意味は〇〇ですか?」といった具合に、相手にフィードバックを求めるのも良いでしょう。
2.2 質問の技術

介護の現場では、利用者一人ひとりの気持ちや行動の背景にある想いを理解することが重要です。
そのためには、適切な質問を投げかけ、相手の思考を深掘りしていくスキルが欠かせません。
特に効果的なのは、「どのように」「なぜ」「どんな」といった開かれた質問(オープンクエスチョン)です。
これらの質問を使うと、単なる事実確認を超えて、より具体的な情報や気づきを引き出すことができます。
例えば、「利用者さんの状態は良いですか?」と聞くよりも、「利用者さんの様子をどのように感じていますか?」と尋ねる方が良いでしょう。
後者の質問なら、相手から利用者の細かな様子について話してもらえるはずです。
さらに踏み込んで質問する技術をご紹介します。
→相手の観察力や状況理解が明らかになります。ケアの現場で起きた出来事の背景が見えてきます。
「その時、どのように対応されましたか?」
→相手の判断力や行動原理が分かります。適切なケアの方法を一緒に検討できます。
「他にどんな方法が考えられそうですか?」
→相手の創造性や問題解決力を引き出せます。新しい発想やアイデアが生まれるかもしれません。
このように、オープンクエスチョンを活用することで、利用者の内面に迫る情報を引き出すことができます。
認知症ケアなどでは特に重要なスキルですね。
また、カンファレンスやケアプラン見直しの際にも、スタッフの気づきを引き出す質問は欠かせません。
チーム全体で情報を共有し、より良いケアの方向性を見出すことができます。
質問力は、介護の現場で不可欠な技術なのです。

Yes/Noで答えられない質問は、気付きを生み出せる。
2.3 効果的なフィードバック
フィードバックは、スタッフの成長を促す重要な要素です。
ただし、単に「良かったですね」と言うだけでは効果は限定的です。
具体的な行動とその効果を結びつけて伝えることが重要です。
例えば、「今日の介助の仕方が良かったです」ではなく、「利用者の表情を見ながらペースを調整していた点が素晴らしかったです。利用者も安心した様子でしたね」というように、具体的に伝えます。
このようなフィードバックのポイントは以下の3つです。
→相手がどのような行動をとったのかを明確に伝える
・相手の努力を認める
→相手の頑張りや工夫を評価する
・その効果も併せて伝える
→その行動がもたらした良い結果を示す
このように、行動と効果を結び付けたフィードバックを心がけることで、相手にとって建設的な情報となります。
単なる賞賛だけではなく、さらなる成長につながるはずです。
介護の現場では、スタッフ一人ひとりの成長が、利用者へのより良いケアに直結します。日頃の業務の中で、効果的なフィードバックを心がけましょう。

具体的な行動と効果を示すことで、スタッフの成長へ!
3. ご家族とのコミュニケーション

家族との対話にもコーチングは効果的です。
家族の不安や心配事を丁寧に聴き取り、共に解決策を考えていく姿勢が重要です。
・家族と協力して利用者理解を深める
・家族の視点を取り入れ、きめ細かなケアを提供する
具体的な質問例としては、以下のようなものがあります。
「現在のケアについて、どのように感じていらっしゃいますか?」
家族と共に、利用者に対する理解を深め、より良いケアの方向性を見出していくことが大切です。
家族は利用者を最もよく知る存在ですから、その視点を取り入れることで、きめ細かなケアの提供につなげられるでしょう。
コーチングの手法を活用すれば、家族の不安や要望に寄り添いながら、共に最適な解決策を見出していくことができます。
4. スタッフのメンタルヘルスケア
介護現場では、スタッフのメンタルヘルスケアが重要な課題となっています。
そこで、コーチングの手法を活用することで、スタッフの悩みや不安を受け止め、共に解決策を見出していくサポートが期待できます。
定期的な面談では、スタッフの思いを丁寧に聴き取ることが重要です。
佐藤「利用者さんの笑顔を見られるときですね。あの喜びの表情を引き出せたときは、本当に嬉しくなります。」
リーダー「そうですね。利用者さんの喜ぶ姿を目にするのは、きっと大きな励みになるんですね。他にも、どのようなことで充実感を感じていますか?」
佐藤「ときどき、ご家族の方から感謝の言葉をいただくことがあるんです。その言葉を聞けば、頑張ってきた甲斐があったと思えます。」
リーダー「ご家族の方からの言葉かけは、スタッフにとってもとても心強いものですね。一方で、どのような困難や悩みを感じていますか?」
佐藤「夜勤の際、認知症の利用者さんの対応に苦慮することが多いです。どう接すればよいかわからず、ストレスを感じることがあります。」
リーダー「夜間の認知症ケアは確かに難しい課題ですね。一緒に、より良い対応方法を考えていきましょう。あなたの経験をもとに、知恵を出し合いましょう。」
このように、否定や批判を避けながら、スタッフの思いに寄り添い、共に解決策を探っていくことが重要です。
小さな成功体験を明らかにしつつ、前に進むためのヒントを見出していきます。
5. まとめ
介護現場でのコーチングは、特別な手法ではありません。
日々の小さなやりとりの中で、相手の考えを引き出し、気づきを促していく。
それが本質です。
この積み重ねが、スタッフ一人ひとりの成長につながり、ひいては介護サービスの質の向上にも結びついていきます。
まずは小さなことから、コーチングを実践してみましょう。
コーチングを身に着けるならFIRST COACH

オンライン特化型コーチングスクール FIRST COACHでは、業界最安値の価格で実践的なコーチングスキルを身に着けることが可能です。
基本からプロレベルまで「現場で使えるコーチング」を専属コーチとの二人三脚で身につけましょう。
新たな可能性を自分自身で広げる一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?
今ならフリーコースとして無料でコーチングの基礎を学び放題。
これからコーチングのスキルを身につけたい方は、ぜひFIRST COACHを受講してみてください!